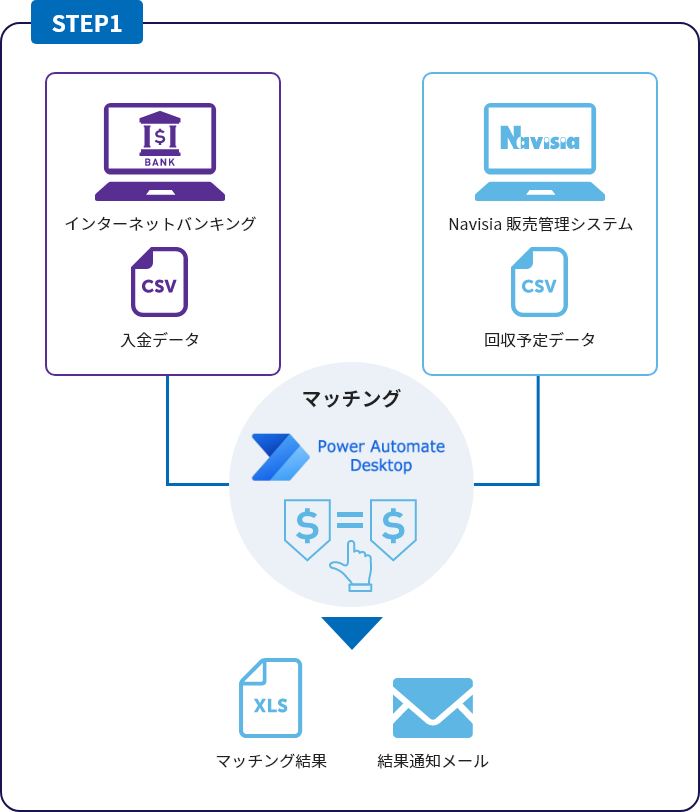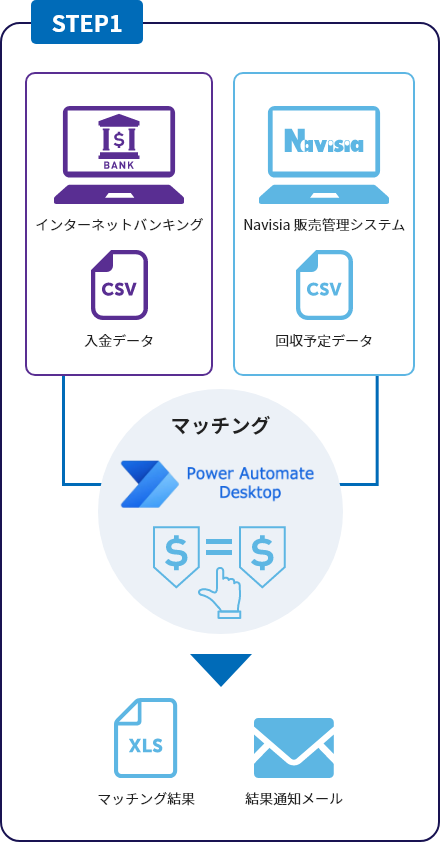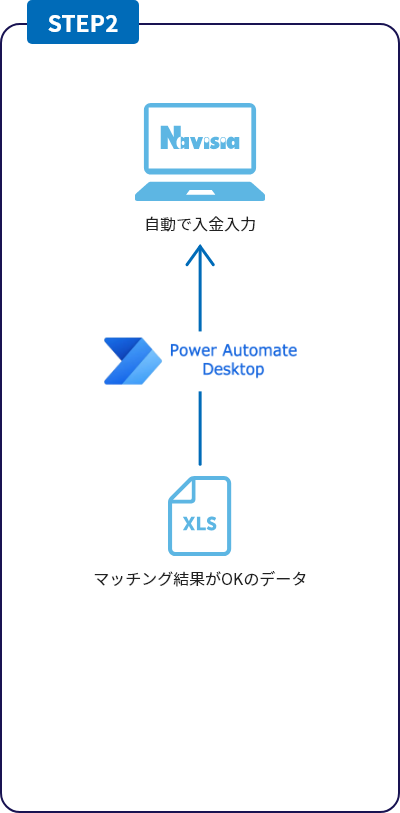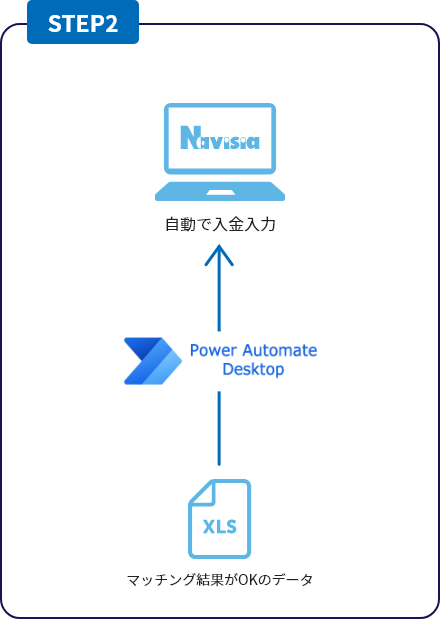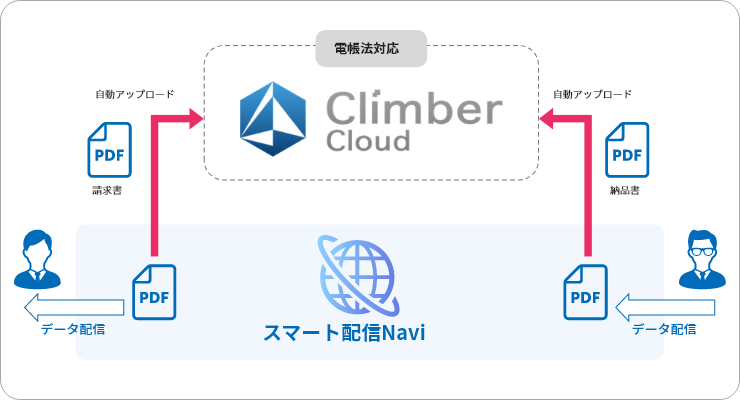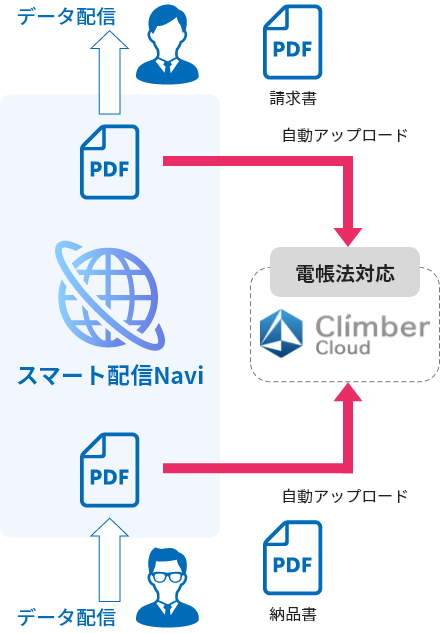| 会社名 | 株式会社ホシケン |
|---|---|
| 業種 | インテリア卸売業 |
| 事業内容 | インテリア商材の卸販売 |
| 従業員数 | 100名 |
| 所在地 | 〒371-0016 群馬県前橋市城東町5-657-18 |
| URL | https://www.hoshiken.com/ |
株式会社ホシケン(以下、ホシケン)は、1905年(明治38年)創業のインテリア総合商社として、壁装材・床材・ブラインドなど多彩な商材を取り扱い、地域の内装業者2,000社以上と信頼を築いてきました。北関東7カ所に展開するジャストインタイム対応の倉庫や、主要メーカーの見本帳を集めたギャラリーを通じて、お客様のインテリアプランを多角的に支援しています。
創業から120年、企業理念である「誠実」を礎に歩み続け、130年という新たな節目に向け、未来への挑戦を続けています。
ホシケンは1995年に販売管理システムのオープン化を実現し、30年という長年に渡り販売管理システムを利用しています。卸売業として要であるジャストインタイムの物流を実現するため、受発注業務の効率化に繋げています。
具体的な活用方法や効果について、代表取締役社長の星野貴洋氏、専務取締役の直江正博氏、総務部チーフマネージャーの桑子真由美氏にお話を伺いました。